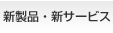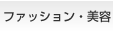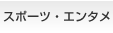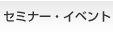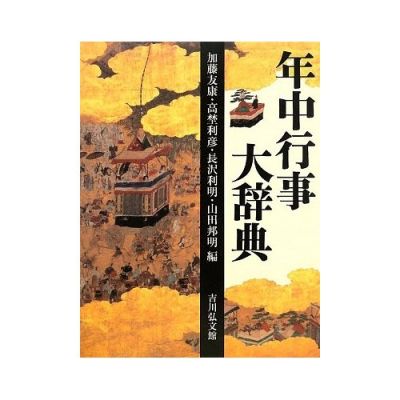新着ニュース30件
2010年9月9日 02:00
一般化しない地味な節句
9月9日は何の日?と聞かれたら、「救急の日」と答える人が殆どに違いない。9月9日は、菊の節句でもあるのだが、端午の節句や、桃の節供は知っているけど、菊は知らないという人が多いのではないだろうか。節句とは、季節の節目に伝統的な行事を行う日のことである。元々は五つあり「五節句」と呼ばれている。1月7日は人日と呼ばれる、七草の節句の日。3月3日は、上巳で桃の節句。5月5日は端午で、菖蒲の節句。7月7日は七夕で笹の節句だ。それぞれ、ご存知のように七草を食べたり、笹を飾ったりするなのど習慣があるのだが、なぜだか9月9日の節句だけ、あまり知られていないのだ。
中国から伝わった陰陽思想では、奇数は陽の数と言われていて、一桁の奇数の中で一番大きな「9」が重なる9月9日は「重陽」と名づけられ、旧暦では菊が花を咲かせる季節でもあるので「菊の節句」とも呼ばれているのである。
菊の節句では、菊の花を飾ったり、菊の花ビラを酒に浮かべた菊花酒を酌み汚れを祓ったりしてきたというのだが、実際に行なっている人は少ない。五節句を今流行の「擬人化」にしてみると、いつもスルーされる菊の節句は「どうせ俺なんて…」と嘆いているに違いない。「菊の節句タンが可哀想!」と、思ってしまった人は、菊花酒でも試してみてはいかがだろうか。風流を楽しむことが出来るはずだ。
年中行事大辞典
-->
記事検索
アクセスランキング トップ10
特集
お問い合わせ