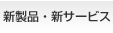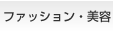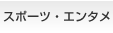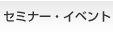新着ニュース30件
2011年10月27日 18:00
2011年10月23日
会場のpetrol blueは、20畳弱ほどの広さ。入口付近にカウンターがあり、奥にステージとしてのスペースを確保するかのように、キーボートとウッドベースが置かれていた。予約だけでソールド・アウトとなった今回のライヴ、開始15分前にほぼ満席。壁に沿って椅子が設置されており、カウンター席と椅子席のわずかな空間が通路だ。通路は1人がやっと通れるほどの狭さ。もちろん離合はかなり難しい。
スタート予定時間から遅れること10分、主役の矢舟テツローが登場。一般客と同じように狭い通路を通る。ライヴは2部制で、1部と2部の間に休憩を挿むスタイル。1部の前半は、鍵盤弾き語りを披露する。鍵盤の上を自由に指が行き来する、というのが容易にわかるほど軽やかな音が連続して並べられ、椅子に座っていなかったら誰もが踊り出していただろう。軽快な鍵盤に負けず劣らず、ヴォーカルも音源より際立っていた。もともと持っている甘い声に、まっすぐに伸びる素直さを感じる。彼のパフォーマンスからは、純粋に音楽が好きだということがひしひしと伝わってくる。そこに邪な気持ちなど一切ない。鍵盤からは音楽を心底楽しもうとする姿勢が、ヴォーカルからは音楽が本当に好きなんだという気持ちが表れていた。
(画像はpetrol blueより)
1部の後半は、ウッドベースに今林良太を迎えて、ベース+鍵盤の2人編成で演奏。鍵盤の浮遊感を優しくサポートするベースによって、どっしりとした安定感が加わる。鍵盤を風船とするならば、ベースは風船についた紐を引っ張る人間だ。地に足がついたベースがあるからこそ、鍵盤が伸び伸びと表現できる。古くからお互いを知る関係が演奏にも鮮やかな相乗効果を生み出していた。
1部終了後、20分ほどの休憩タイム。演者の2人はいったんステージを離れた。休憩中はドリンクを注文したり、話をしたりと皆思い思いに楽しんでいた。20分後、矢舟テツローがまた狭い通路を通って1人だけステージに戻ってきた。
2部の前半2曲は、鍵盤弾き語り。先ほどの安定感は影を潜め、鍵盤だけでどこまでも攻め続ける彼の姿が印象的だった。音源はジャズとポップスの要素が半々、といった分量ではあったが、ライヴではもっとジャズ寄りで、生演奏ならではの生命力を感じる。音源にはない隠し味が、ライヴには加えられている。
2部の後半は、再度今林良太を迎えて演奏。ウッドベースによって曲の輪郭が明確になり、境界線が見えてくる。そのことで散っていた音が一塊りになって会場を包み始める。広い会場では、オーソドックスなバンド・スタイルのほうが弾き語りとの区別がはっきりするだろう。しかし、今回のような50人ほどでいっぱいの会場では、ウッドベースが加わるだけでもその違いはダイレクトに伝わる。一度のライヴで2通りの楽しみ方がある粋な計らいだ。
(画像はpetrol blueより)
アンコールでは通路が狭いということもあったのか、下がらずに一呼吸置いてそのまま始めてしまう融通の利く一面も見せた。休憩とアンコール含めて2時間半、サービス精神旺盛にたっぷりと演奏。ステージから下がった後、エレベーター付近で帰る人々に『ありがとうございました』と別れの挨拶をする彼の姿を見た時にふと思った。確かな実力と礼儀を兼ね備えている男に、欠点などあるのだろうか、と。
(松本 良太)
-->
記事検索
アクセスランキング トップ10
特集
お問い合わせ